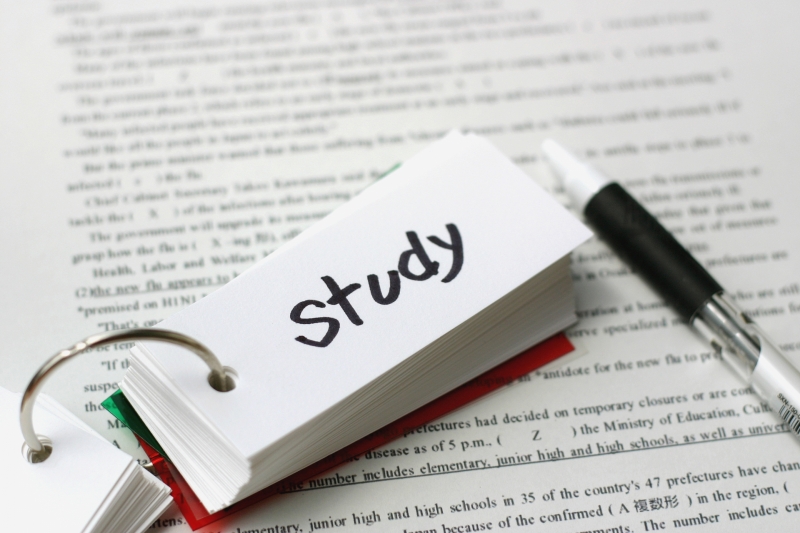
前処理工程は、材料に合わせた処理が大切なことは前回の記事でおわかり頂けたかと思います。
第4回 下地めっき:銅めっきとニッケルめっき
めっきといっても様々な種類がありますが、まずは下地として使われるめっきについてお話ししましょう。
そもそもなぜ下地めっき加工が必要なのでしょうか。
めっき処理を化粧への例えとして、別ページで説明しましたが、下地めっき=下地作りと考えられます。
下地の表面を平滑にして、化粧が乗りやすくする。そんなイメージをもってください。
めっきにおける下地めっきとして使われる主なめっきが以下の2種類です。
銅めっき(Cuめっき)
特徴
金属としての銅は金、銀とともに特有の色を持つ有色金属で、古くは「あかがね」と称し、赤い色調を持っています。
電気伝導性と熱伝導性に優れています。
ここでは、下地めっきとして紹介しますが、他には銅箔の製造、プリント配線板のスルーホールやビアホール、生活用品としてはフライパン底部に使われたりする金属めっきとなります。
主な銅めっきとして以下の種類があります。
| 銅めっき種 | 特徴 |
| シアン化銅めっき | 均一な電着が可能で、密着性のよい皮膜が形成できます。 ただ、毒性の強いシアン化合物を使用しているため、適切な設備や管理が必要になります。 |
| 硫酸銅めっき | 1945年以前は、銅めっき=硫酸銅めっきと言われるぐらい主流のめっきでした。 めっき浴の管理に優れ、室温でめっきが可能です。 |
| ピロリン酸銅めっき | 公害規制が厳しくなり、導入されためっき浴になります。 弱アルカリ性で、均一電着性に優れています。 |
ニッケルめっき(Niめっき)
特徴
ニッケルめっきは耐食性に優れており、硬度があり強靭な性質を持つので、鉄鋼や銅合金、亜鉛合金、アルミニウム合金など各種素材に対して防食と装飾の役割を果たすことが可能です。ニッケルアレルギーの原因物質であることから、人体に直接触れるものには仕上げめっきとしては使われないめっき皮膜でもあります。
主なニッケルめっきとして以下の種類があります。(めっき浴で表現されることが多いです)
| 銅めっき種 | 特徴 |
| ワット浴 | 硫酸ニッケルを主成分とした一般的なニッケルめっきです。 |
| スルファミン酸浴 | スルファミン酸ニッケルを主成分としたニッケルめっきになります。 高い電流密度で使用でき、内部応力が低い特徴があるため、内部応力を避けたい部材に最適です。 |
| ウッド浴 | 塩化ニッケルを主成分としたニッケルめっきになります。ステンレスのような表面に酸化皮膜を作りやすい金属上に密着性のよいめっきをする際に使用されます。 |
ニシハラ理工でも上記で説明させて頂きましたシアン化銅めっき、スルファミン酸ニッケルめっきを扱っています。
材料やめっき加工の詳細は、めっき加工可能一覧表もあわせてご覧ください。
めっき仕様一覧
次の記事では仕上めっき加工についてお話します。
参考文献
新めっき技術(関東学院大学出版界)丸善出版株式会社



